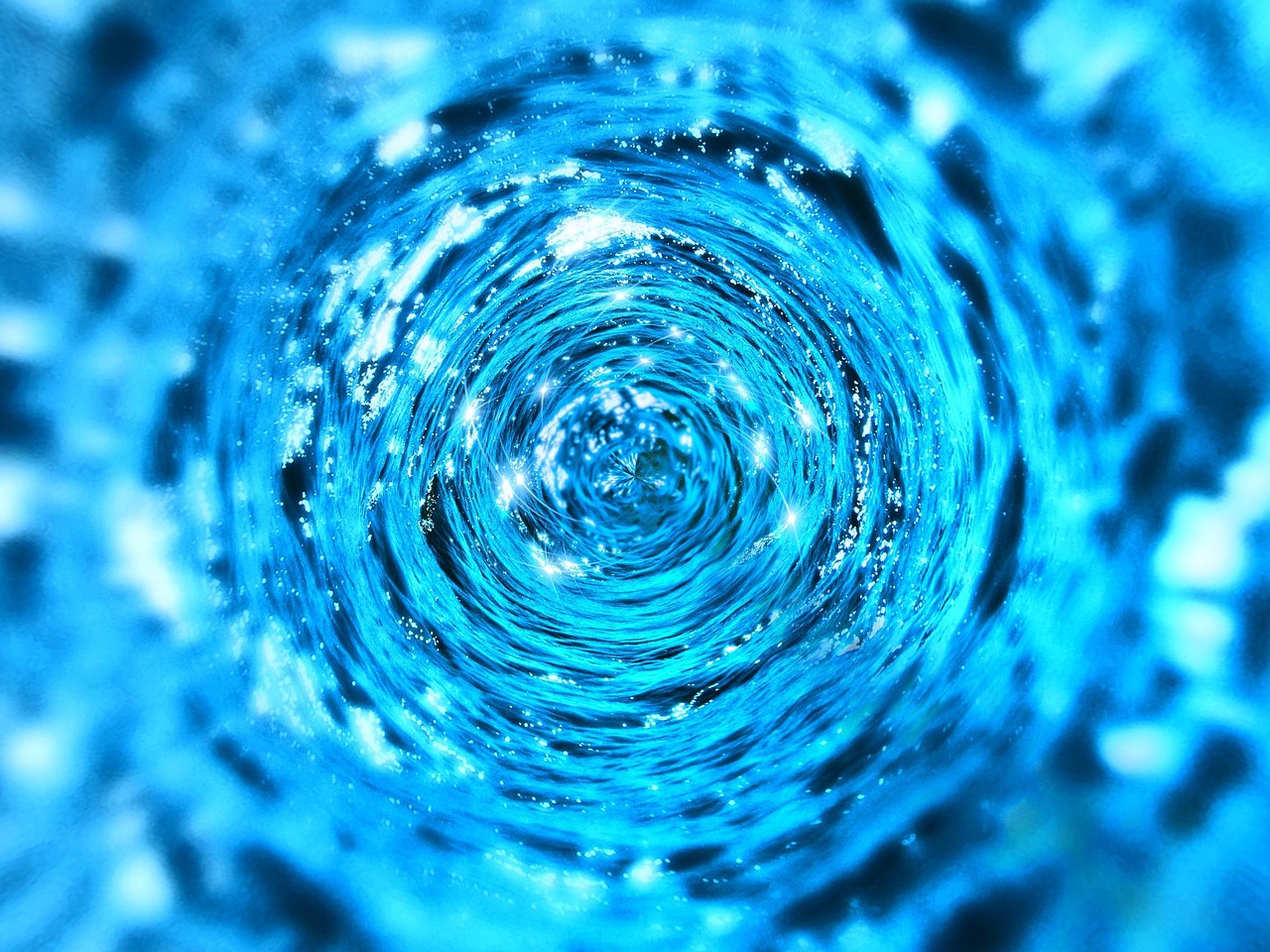文壇を揺るがす新たな論争が勃発しています。直木賞作家の篠田節子さんが執筆した新作小説『青の純度』が、クリスチャン・ラッセンをモデルにした内容である中、ラッセン研究家の原田裕規さんが自身の著書との類似を指摘。これに対し、出版社の集英社が発表した声明が波紋を呼び、内容の一部が削除される事態に発展しました。この騒動の裏側を、事実に基づいて紐解いていきます。
この記事のまとめ
- 原田裕規さんが書評で『青の純度』と自身のラッセン関連著書の類似点を指摘し、参考文献未記載を問題視。
- 集英社は声明で「著者は原田さんの書籍を読んでおらず、独自取材に基づく」と反論し、風評被害に抗議。
- 声明に含まれた「図書館で借りたが読まずに返却」の記述が削除され、対応に疑問の声が上がる。
- 篠田節子さんはインタビューで、ラッセンとの出会いを自身の息抜きとして語っており、創作の原点を明かす。
ラッセン小説パクリ疑惑で出版社大慌て!
この騒動の火種は、原田裕規さんの書評にあります。原田さんは、ラッセンを専門に研究するアーティストで、『ラッセンとは何だったのか?』や『評伝クリスチャン・ラッセン』などの著書を刊行しています。2025年10月16日、原田さんは共同通信を通じて全国各紙に書評を配信しました。そこで、『青の純度』に登場する「マリンアートの巨匠」がラッセンをモデルにしている点を認めつつ、自身の著書にしかない独自の事実が小説に反映されているのに、参考文献リストに記載がないことを疑問視しました。
原田さんは書評の中で、「本書にはラッセンや拙著の名前は一度も登場せず、巻末の参考文献リストを見ても、拙著にまつわる情報が周到に排除されていました」と指摘しています。 さらに、「願わくば適切な手続きのもとで記されてほしい」と、穏やかながらもクレジットを求める立場を明確にしました。この指摘は、単なる類似ではなく、研究者の労力を尊重する観点から来ており、文壇の倫理を問う声として広がりました。
これに対し、集英社は即座に反応を示しました。10月24日、同社の文芸編集部は公式サイト「集英社 文芸ステーション」で声明を発表。著者の篠田節子さんが原田さんの書籍を読んでおらず、独自の取材に基づいて執筆したと主張しました。 しかし、この声明には「篠田氏が『ラッセンとは何だったのか?』を図書館で借りた事実はあるものの、内容を読まずに返却したため、参照はしていない」という記述が含まれ、ネット上で「苦しい言い訳」との批判を浴びました。原田さん自身もX上でこの回答を共有し、事実確認の結果を公表しています。
出版社の慌てぶりが顕著になったのは、この記述の削除です。声明発表直後、ネットユーザーが指摘する中で、該当部分が公式サイトから忽然と消えました。集英社は書評を「一方的にご意見を表明されたことに対して大変遺憾」とし、「風評被害に断固抗議いたします」と強い調子で反論を続けていますが、削除の理由については一切触れていません。この対応が、かえって疑惑を深め、出版社の危機管理の甘さを露呈した形となりました。
原田裕規さんの指摘の詳細
原田裕規さんの書評は、単なる不満表明ではなく、具体的な類似点を挙げています。例えば、『青の純度』ではラッセンの生涯や作品のエピソードがフィクションとして描かれていますが、これらが原田さんの著書で独自に掘り下げられた内容と重なる点が多いのです。原田さんは「自著にしかない事実が小説内にある」と述べ、研究の独自性を強調しました。
原田さんはアーティストとしても活躍しており、TERRADA ART AWARD 2023を受賞するなど、美術界で評価が高い人物です。この指摘は、創作の自由と他者の知的財産尊重のバランスを問うもので、文芸界全体に示唆を与えています。原田さん自身は、X上で「今はひとまず待機していようと思います」と冷静な姿勢を示していますが、声明の削除についてはさらなる展開を注視しているようです。
集英社の声明と削除の経緯
集英社の声明は、発表当初から物議を醸しました。全文では、「弊社刊『青の純度』につきまして」と題され、著者の取材プロセスを詳細に説明。原田さんの他の著作も読んでいないとし、独自性を強調しています。しかし、「借りたが読まず」の一文が最大の火種となりました。この記述は、図書館の貸出記録を前提としたもので、事実確認の厳密さを示唆しますが、逆に「読まなかった」という主張の信憑性を損なうものとして批判されました。
削除の経緯は、X上でのユーザー指摘がきっかけです。発表から数時間で、該当部分がサイトから除去され、声明のトーンがやや柔らかくなったとの声もあります。集英社はこれを「風評に抗議」と位置づけていますが、削除自体が出版社の後手後手の対応を象徴しています。 この一件は、デジタル時代の声明管理の難しさを浮き彫りにしました。
篠田節子さんの創作背景
騒動の中心である篠田節子さんは、直木賞受賞の実力派作家です。『青の純度』の創作意図について、集英社の公式インタビューで語っています。篠田さんは、「仕事と介護でくたびれ果てると、母を寝かせた後に車で片道一時間半かけて山中湖のリゾートホテルに出かけて朝帰ってくる、というのが唯一の息抜きでした。ある時、そのホテルの地下へ行ってみたらクリスチャン・ラッセンの絵があったんです」と振り返っています。
さらに、「この絵の中に入り込んで、現実に帰ってきたくないな、と……。国内旅行すらもままならない中で、どこか遠くへ行きたいという願望の象徴が、南の島だったんです。そういった状況にラッセンの絵がぴったりハマって、ぼーっと見入ってしまった」と続けています。この個人的な体験が小説の基盤となっており、ラッセンを「逃避の象徴」として描いたことがわかります。インタビューでは、独自の取材を強調しており、出版社の主張とも一致します。
さいごに
この騒動は、創作のインスピレーション源とクレジットの重要性を改めて考えさせる出来事です。原田裕規さんの指摘は研究者の尊厳を守るものとして、集英社の対応は出版社の責任を問うものとして、両者の対立が文壇の議論を活発化させています。最終的な解決は当事者間の対話に委ねられますが、読者として『青の純度』や原田さんの著書を手に取り、自身の目で確かめてみるのが一番です。創作の喜びと倫理の狭間で、何が生まれるのか。今後の展開に注目しましょう。